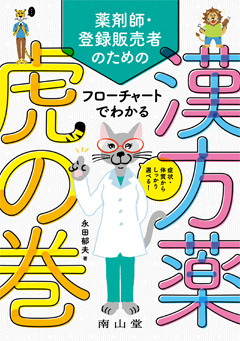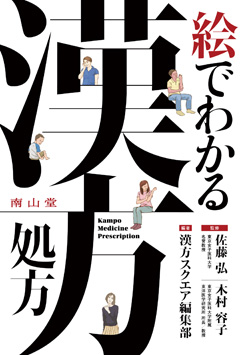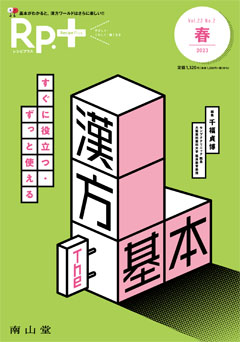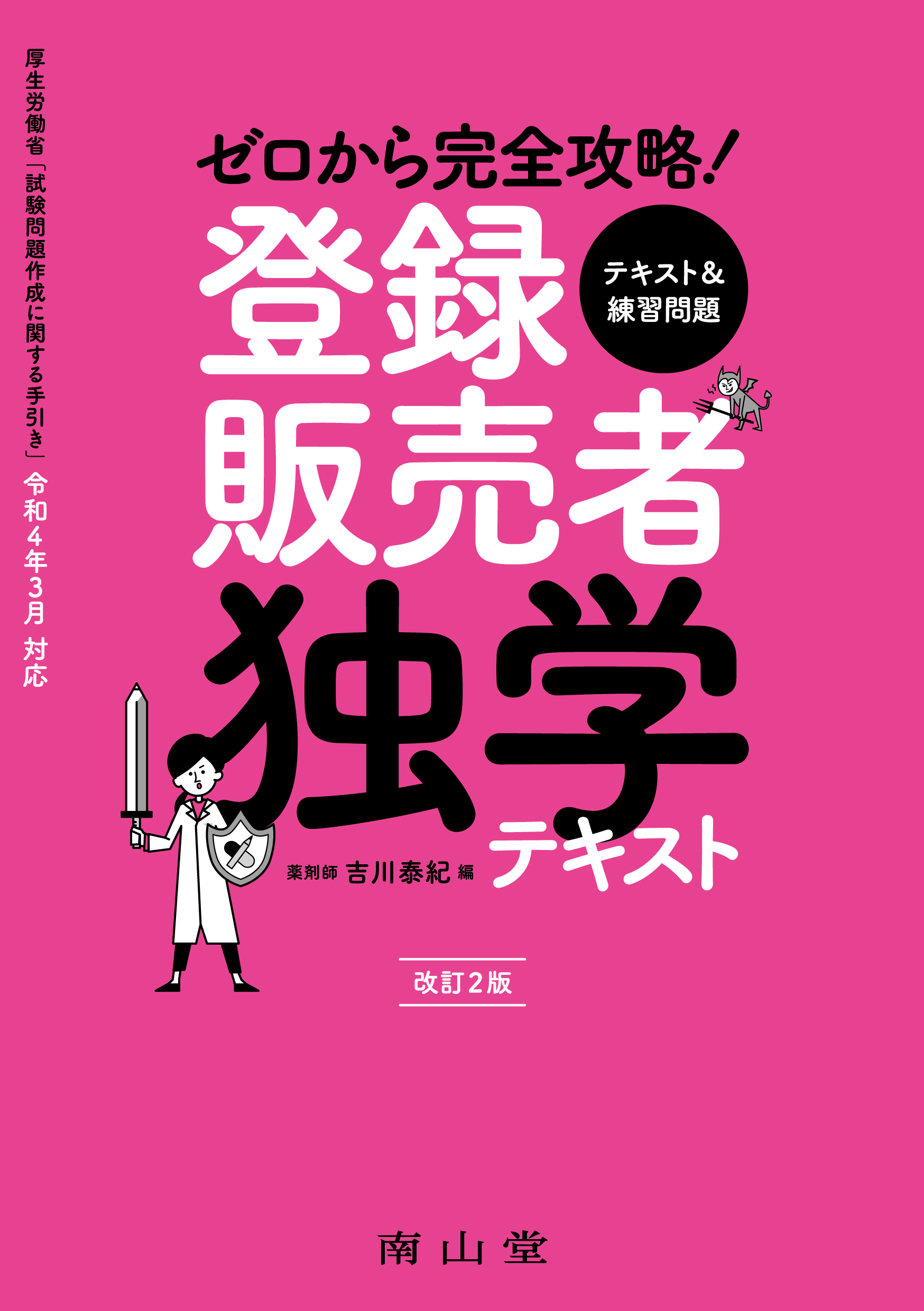症状・体質からしっかり選べる!
薬剤師・登録販売者のための フローチャートでわかる漢方薬虎の巻
1版
永田郁夫 著
定価
2,640円(本体 2,400円 +税10%)
- A5判 140頁
- 2023年8月 発行
- ISBN 978-4-525-47171-2
症状・体質にあった漢方が分かる!選べる!!
漢方医学では「証」や「気血水」などの症状・体質から治療法を決めます.ですが,「用語が難しい」「どう活かせばいいか分からない」など困ったことはないでしょうか.
そんな悩みを解決すべく,本書では体質・症状にあう漢方薬の選びかたをフローチャートで解説しました! 選び方の流れを身につけることで,自然と「証」「気血水」などの意味・使いかたも分かるようになっています.
初学者はもちろん,漢方をより深く知りたい人にもおすすめの一冊です.
- 序文
- 目次
- 書評1
- 書評2
- 書評3
- 編集部より
序文
西暦 650 年頃に記された中国古典に「千金要方(せんきんようほう)」という医学書があります.それには,医師を上医,中医,下医の 3 段階に分けており,最も優れた医師,つまり上医は,まだ病気になる前の状態(未病)を治す医師のことであるという考え方が記されています.ここから,予防医学を重視した考え方はすでに約 1400 年前からあったことがわかります.
この未病を治す大切さと未病に対する漢方薬の必要性は大きくつながります.また,未病の思想は養生の重要性に結びつきます.漢方医学は予防医学でもあり養生医学でもあります.生体が本来もっている自然治癒力を高める,あるいは導き出すことを基本理念としています.
本書では,改善したい症状について漢方薬をフローチャートで選べるように解説しています.フローチャートは,患者の「証」を確定するための虚実[病勢],寒熱[病性],気血水[病態]などを考慮して作成しました.その際,寒熱[病性]の表現は各書籍によって多少異なるため,読者のみなさまが現場で混乱せずに漢方薬を選択できるよう,株式会社ツムラの「ツムラ医療用漢方製剤」に統一しました.
さて,「証」には主証と客証があります.主証は主になる症状であり,ある一定期間ほとんど変動がありません.しかし,客証は主証に付随して一時的にあらわれる症状であり,あったりなかったりして変わります.例えば,「加味逍遥散(かみしょうようさん)証」では〝のぼせ,イライラ〟などは主証と考えられ,〝めまい,口渇,手足の冷え〟などは客証と考えられます.また,症状として〝しみや肌あれ,めまい,不眠〟などがある場合,これは,気血水[病態]では「血虚」の場合でも「血滞」の場合でもあらわれる症状です.すなわち,主証と客証の「症状」,さらには[病勢],[病性],[病態]などの捉え方によって,漢方薬の選択肢も変わってきます.そのため,症状からフローチャートのみで症状にあった漢方薬を選択するのは多少難がありますが,最も適した漢方薬を選択するヒントになれば幸いです.
なお,各項目で代表的な漢方薬を紹介しますが,患者の「証」は一人ひとり違い,それによって漢方薬も異なるのが本来の漢方医学の基本概念です.ゆえに,今回取り上げた漢方薬以外でも,各個人に合った漢方薬があるのはいうまでもありません.
薬局やドラックストアはもちろん,病院などでも漢方薬を選択する際にお役に立つよう執筆しました.ぜひ本書を活用して頂ければ幸いです.
2023年6月
永田郁夫
この未病を治す大切さと未病に対する漢方薬の必要性は大きくつながります.また,未病の思想は養生の重要性に結びつきます.漢方医学は予防医学でもあり養生医学でもあります.生体が本来もっている自然治癒力を高める,あるいは導き出すことを基本理念としています.
本書では,改善したい症状について漢方薬をフローチャートで選べるように解説しています.フローチャートは,患者の「証」を確定するための虚実[病勢],寒熱[病性],気血水[病態]などを考慮して作成しました.その際,寒熱[病性]の表現は各書籍によって多少異なるため,読者のみなさまが現場で混乱せずに漢方薬を選択できるよう,株式会社ツムラの「ツムラ医療用漢方製剤」に統一しました.
さて,「証」には主証と客証があります.主証は主になる症状であり,ある一定期間ほとんど変動がありません.しかし,客証は主証に付随して一時的にあらわれる症状であり,あったりなかったりして変わります.例えば,「加味逍遥散(かみしょうようさん)証」では〝のぼせ,イライラ〟などは主証と考えられ,〝めまい,口渇,手足の冷え〟などは客証と考えられます.また,症状として〝しみや肌あれ,めまい,不眠〟などがある場合,これは,気血水[病態]では「血虚」の場合でも「血滞」の場合でもあらわれる症状です.すなわち,主証と客証の「症状」,さらには[病勢],[病性],[病態]などの捉え方によって,漢方薬の選択肢も変わってきます.そのため,症状からフローチャートのみで症状にあった漢方薬を選択するのは多少難がありますが,最も適した漢方薬を選択するヒントになれば幸いです.
なお,各項目で代表的な漢方薬を紹介しますが,患者の「証」は一人ひとり違い,それによって漢方薬も異なるのが本来の漢方医学の基本概念です.ゆえに,今回取り上げた漢方薬以外でも,各個人に合った漢方薬があるのはいうまでもありません.
薬局やドラックストアはもちろん,病院などでも漢方薬を選択する際にお役に立つよう執筆しました.ぜひ本書を活用して頂ければ幸いです.
2023年6月
永田郁夫
目次
第Ⅰ章 漢方薬の基本
01.漢方薬とは
02.症状・体質にあう漢方薬とは
03.漢方薬の服用方法
04.医療用と一般用の漢方製剤の違い
05.漢方薬とドーピングのかかわり
06.重複に注意する生薬
第Ⅱ章 漢方医学での症状・体質の捉えかた
01.病性 「寒」〈陰〉―「熱」〈陽〉
02.病勢 「実」―「中」―「虚」
03.外邪
04.気血水
05.帰経
06.表と裏
07.病期
08.病向
第Ⅲ章 主訴・症状別 漢方薬の使い分け
01.頭痛
02.二日酔い
03.冷え症
04.疲れ・夏バテ
05.虚弱体質
06.口渇・口乾
07.肥満
08.痩身
09.神経痛(痛みとしびれ)
10.不眠
11.イライラ
12.不安症・抑うつ
13.寝汗・多汗
14.感冒
15.のどの痛み(咽頭炎)
16.咳・痰
17.鼻炎・花粉症
18.動悸・頻脈(心悸亢進)
19.むくみ
20.食欲不振・胃もたれ・胸やけ・げっぷ
21.嘔吐
22 腹痛・胃痛
23.下痢
24.便秘
25.痔
26.頻尿・尿トラブル
27.めまい
28.耳鳴り
29.月経痛・月経困難症
30.更年期障害
31.腰痛・下肢痛
32.関節痛・腫れ
33.肩こり
34.こむら返り
第Ⅳ章 漢方方剤一覧
索引
01.漢方薬とは
02.症状・体質にあう漢方薬とは
03.漢方薬の服用方法
04.医療用と一般用の漢方製剤の違い
05.漢方薬とドーピングのかかわり
06.重複に注意する生薬
第Ⅱ章 漢方医学での症状・体質の捉えかた
01.病性 「寒」〈陰〉―「熱」〈陽〉
02.病勢 「実」―「中」―「虚」
03.外邪
04.気血水
05.帰経
06.表と裏
07.病期
08.病向
第Ⅲ章 主訴・症状別 漢方薬の使い分け
01.頭痛
02.二日酔い
03.冷え症
04.疲れ・夏バテ
05.虚弱体質
06.口渇・口乾
07.肥満
08.痩身
09.神経痛(痛みとしびれ)
10.不眠
11.イライラ
12.不安症・抑うつ
13.寝汗・多汗
14.感冒
15.のどの痛み(咽頭炎)
16.咳・痰
17.鼻炎・花粉症
18.動悸・頻脈(心悸亢進)
19.むくみ
20.食欲不振・胃もたれ・胸やけ・げっぷ
21.嘔吐
22 腹痛・胃痛
23.下痢
24.便秘
25.痔
26.頻尿・尿トラブル
27.めまい
28.耳鳴り
29.月経痛・月経困難症
30.更年期障害
31.腰痛・下肢痛
32.関節痛・腫れ
33.肩こり
34.こむら返り
第Ⅳ章 漢方方剤一覧
索引
書評1
俣賀 隆(仁保病院 薬剤部/山口市薬剤師会副会長)
本書の最も大きな特徴は,薬剤師・登録販売者の方々が薬局や病院などである症状に適合する漢方薬を患者や来店者,漢方専門外の医師などより相談された際に,体質やその症状をYes・No のフローチャートで辿って行くことで適合する漢方薬を選定できるよう「第Ⅲ章 主訴・症状別 漢方薬の使い分け」で図示されている点です.
保険適応病名から漢方薬を検索すると複数の漢方薬がヒットします.通常,症状に応じた漢方薬を決定するには,陰陽や虚実,気血水など,その患者の全身を診て時間と共に変化していく「証」を判断することになります.本書は,証を判断する知識がさほど無くても現在の症状,体質に適合する漢方薬を選定することが出来るよう構成されています.また各症状の項目には「こんな人には受診勧奨を!」として,その症状のなかに潜んでいる可能性がある受診勧奨すべき重大な疾患が記述されており,症状のみを診るのではなく,患者全体の観察を忘れないようにとの著者の思いが見て取れます.「第Ⅳ章 漢方方剤一覧」の活用方法の一例として,第Ⅲ章でフローチャートに沿って選定した漢方薬が,相談者の症状・体質(病性や病勢,外邪,気血水,病向,帰経)に適合しているかを再確認するために利用されるのがよいと考えます.そのためには,「第Ⅰ章 漢方の基本」「第Ⅱ章 漢方医学での症状,体質の捉え方」を熟読することが肝要です.
私達が本を購入して知識やスキルを習得したい時,誰しも効率的に学びたいと考えるのではないでしょうか.そのためには,購読した本が効率的,体系的に構成されている必要があります.本書はその点,忙しい方でも短時間で漢方治療の実践ができる数少ない著書だと思います.漢方薬は実際に使用して経験を積み重ねて熟練者になります.本書のフローチャートで選定した漢方薬を試して適合例もある一方で,なかにはうまく適合しない例もあると思います.不適合例ではほかのフローでの漢方薬適合性を思考することで,漢方診断の更なるステップアップが図れるのではないでしょうか.病名(症状)=漢方薬をあてはめるのではなく,相談者の証に適合する漢方薬の選定方法を学ぼうとしている薬剤師・登録販売者の方々にとって,まさに「虎の巻」の一冊としてご活用されることを切に願います.
本書の最も大きな特徴は,薬剤師・登録販売者の方々が薬局や病院などである症状に適合する漢方薬を患者や来店者,漢方専門外の医師などより相談された際に,体質やその症状をYes・No のフローチャートで辿って行くことで適合する漢方薬を選定できるよう「第Ⅲ章 主訴・症状別 漢方薬の使い分け」で図示されている点です.
保険適応病名から漢方薬を検索すると複数の漢方薬がヒットします.通常,症状に応じた漢方薬を決定するには,陰陽や虚実,気血水など,その患者の全身を診て時間と共に変化していく「証」を判断することになります.本書は,証を判断する知識がさほど無くても現在の症状,体質に適合する漢方薬を選定することが出来るよう構成されています.また各症状の項目には「こんな人には受診勧奨を!」として,その症状のなかに潜んでいる可能性がある受診勧奨すべき重大な疾患が記述されており,症状のみを診るのではなく,患者全体の観察を忘れないようにとの著者の思いが見て取れます.「第Ⅳ章 漢方方剤一覧」の活用方法の一例として,第Ⅲ章でフローチャートに沿って選定した漢方薬が,相談者の症状・体質(病性や病勢,外邪,気血水,病向,帰経)に適合しているかを再確認するために利用されるのがよいと考えます.そのためには,「第Ⅰ章 漢方の基本」「第Ⅱ章 漢方医学での症状,体質の捉え方」を熟読することが肝要です.
私達が本を購入して知識やスキルを習得したい時,誰しも効率的に学びたいと考えるのではないでしょうか.そのためには,購読した本が効率的,体系的に構成されている必要があります.本書はその点,忙しい方でも短時間で漢方治療の実践ができる数少ない著書だと思います.漢方薬は実際に使用して経験を積み重ねて熟練者になります.本書のフローチャートで選定した漢方薬を試して適合例もある一方で,なかにはうまく適合しない例もあると思います.不適合例ではほかのフローでの漢方薬適合性を思考することで,漢方診断の更なるステップアップが図れるのではないでしょうか.病名(症状)=漢方薬をあてはめるのではなく,相談者の証に適合する漢方薬の選定方法を学ぼうとしている薬剤師・登録販売者の方々にとって,まさに「虎の巻」の一冊としてご活用されることを切に願います.
書評2
赤瀬朋秀(日本経済大学大学院経営学研究科教授)
くすりを題材にした研修会やセミナーのなかでも,漢方薬を主題にしたものは集客がよいと聞き及ぶ。すなわち,漢方薬というくすりは,薬剤師にとって馴染みやすく身近なものであるが,その一方で,難解な東洋医学の理論を理解するためには相応の時間を割いて勉強をしなければならないという面も有する。それだけに,漢方薬の適正使用に資する医薬品情報は,薬剤師にとって関心の深い分野であると感じている。 しかしながら,実際に薬剤師が処方監査や服薬指導をする際に,この漢方薬が目の前の患者に適しているのか,どのように説明をしたらよいのか悩むことが多い。さらに,そのようなときに真っ先に手にすべき書籍を探すと,“ありそうでない”のが実情である。特に,“初学者にとってわかりやすい”という条件を付加すると,“なさそうだけれど本当にない”というのが現状であった。かくして,手あたり次第に種々の書籍を読み漁ることになる。
今回,永田先生が記した「薬剤師・登録販売者のための フローチャートでわかる漢方薬虎の巻」は,そんな薬剤師の悩みを解決するのに丁度よく,特に,感冒,頭痛,鼻炎,便秘といった日常よくみる疾患や症候に対し,フローチャートでどういった方剤が適しているか示してくれている。これならば登録販売者が漢方薬を選択する一つの基準にもなりうる。さらにページを進めると,方剤の東洋医学的な解説がなされており,さらに深く勉強したい場合にも適した構成になっている。
筆者の永田郁夫先生とのお付き合いはもう30年にも及ぶであろうか。当時を振り返ると,勤務先は違えど,お互いに東洋医学・漢方薬の医薬品情報や服薬指導などについてともに切磋琢磨しあった戦友でもある。当時,永田先生とは,年に1回程度であったが,日本東洋医学会などの学会でお目にかかり,互いの発表に耳を傾けあい,ときには質問や議論を交わしながら相互に知識を高めあった仲でもある。
そんな先生が記した書籍だからこそ,間違いのない良書といえよう。昨今の医薬品を取り巻くイノベーションの影響により,薬物療法そのものが以前と比較して格段に進歩している。しかし,ときには漢方薬のような長い歴史のある医薬品を勉強することも,薬を扱う薬剤師や登録販売者にとって必要なのではないだろうか。自信をもってお勧めしたい一冊である。
くすりを題材にした研修会やセミナーのなかでも,漢方薬を主題にしたものは集客がよいと聞き及ぶ。すなわち,漢方薬というくすりは,薬剤師にとって馴染みやすく身近なものであるが,その一方で,難解な東洋医学の理論を理解するためには相応の時間を割いて勉強をしなければならないという面も有する。それだけに,漢方薬の適正使用に資する医薬品情報は,薬剤師にとって関心の深い分野であると感じている。 しかしながら,実際に薬剤師が処方監査や服薬指導をする際に,この漢方薬が目の前の患者に適しているのか,どのように説明をしたらよいのか悩むことが多い。さらに,そのようなときに真っ先に手にすべき書籍を探すと,“ありそうでない”のが実情である。特に,“初学者にとってわかりやすい”という条件を付加すると,“なさそうだけれど本当にない”というのが現状であった。かくして,手あたり次第に種々の書籍を読み漁ることになる。
今回,永田先生が記した「薬剤師・登録販売者のための フローチャートでわかる漢方薬虎の巻」は,そんな薬剤師の悩みを解決するのに丁度よく,特に,感冒,頭痛,鼻炎,便秘といった日常よくみる疾患や症候に対し,フローチャートでどういった方剤が適しているか示してくれている。これならば登録販売者が漢方薬を選択する一つの基準にもなりうる。さらにページを進めると,方剤の東洋医学的な解説がなされており,さらに深く勉強したい場合にも適した構成になっている。
筆者の永田郁夫先生とのお付き合いはもう30年にも及ぶであろうか。当時を振り返ると,勤務先は違えど,お互いに東洋医学・漢方薬の医薬品情報や服薬指導などについてともに切磋琢磨しあった戦友でもある。当時,永田先生とは,年に1回程度であったが,日本東洋医学会などの学会でお目にかかり,互いの発表に耳を傾けあい,ときには質問や議論を交わしながら相互に知識を高めあった仲でもある。
そんな先生が記した書籍だからこそ,間違いのない良書といえよう。昨今の医薬品を取り巻くイノベーションの影響により,薬物療法そのものが以前と比較して格段に進歩している。しかし,ときには漢方薬のような長い歴史のある医薬品を勉強することも,薬を扱う薬剤師や登録販売者にとって必要なのではないだろうか。自信をもってお勧めしたい一冊である。
書評3
岡野善郎(徳島文理大学 名誉教授)
本書は,その書名“漢方薬虎の巻”が示すように,わかりやすく親しみやすくまとめられています.
この虎の巻を開くと,各ページが漢方の奥深い世界に誘ってくれます.たとえば,病気になる前の状態(未病)を治す大切さと未病に対する漢方薬(漢方方剤)の選択の根拠・背景などが解説されています.
読者対象は薬局・ドラッグストア・病院などで漢方薬を取り扱う薬剤師・登録販売者とし,“症状による漢方薬の使い分け”をフローチャートで解説しています.加えて“病性”,“病勢”,“気血水”などの漢方医学の基礎から各漢方薬の特徴まで網羅されており,初学者・薬学生にも手に取りやすい書籍になっています.本書の構成は,第Ⅰ章「漢方薬の基本」,第Ⅱ章「漢方医学での症状・体質の捉えかた」,第Ⅲ章「主訴・症状別 漢方薬の使い分け」,第Ⅳ章「漢方方剤一覧」です.
特徴は,第Ⅲ章のフローチャートで34項目の主訴・症状(たとえば,頭痛や二日酔いなど)に対する漢方薬の使い分けが提示されている点です.ここには著者の新しい試みとして漢方薬選択のヒントがフローチャートを使って図示されています.なお,正しいフローチャートの使い方の解説書はありません.そのため読者自身でフローチャートをどう使うか,自分で工夫する余地があります.工夫の一例としてフローチャート中に見聞きした情報(患者・顧客等との対話ややりとりなど)を追記することなどがあります(たとえば,朱色を入れる,メモを貼るなど).
繰り返しになりますが,本書はフローチャートの活用で漢方薬をうまく選択する第一歩となり得ることを明示した読本であり,漢方薬全般の理解および漢方薬の使い分けの根拠の一助となる良書です.
本書は,その書名“漢方薬虎の巻”が示すように,わかりやすく親しみやすくまとめられています.
この虎の巻を開くと,各ページが漢方の奥深い世界に誘ってくれます.たとえば,病気になる前の状態(未病)を治す大切さと未病に対する漢方薬(漢方方剤)の選択の根拠・背景などが解説されています.
読者対象は薬局・ドラッグストア・病院などで漢方薬を取り扱う薬剤師・登録販売者とし,“症状による漢方薬の使い分け”をフローチャートで解説しています.加えて“病性”,“病勢”,“気血水”などの漢方医学の基礎から各漢方薬の特徴まで網羅されており,初学者・薬学生にも手に取りやすい書籍になっています.本書の構成は,第Ⅰ章「漢方薬の基本」,第Ⅱ章「漢方医学での症状・体質の捉えかた」,第Ⅲ章「主訴・症状別 漢方薬の使い分け」,第Ⅳ章「漢方方剤一覧」です.
特徴は,第Ⅲ章のフローチャートで34項目の主訴・症状(たとえば,頭痛や二日酔いなど)に対する漢方薬の使い分けが提示されている点です.ここには著者の新しい試みとして漢方薬選択のヒントがフローチャートを使って図示されています.なお,正しいフローチャートの使い方の解説書はありません.そのため読者自身でフローチャートをどう使うか,自分で工夫する余地があります.工夫の一例としてフローチャート中に見聞きした情報(患者・顧客等との対話ややりとりなど)を追記することなどがあります(たとえば,朱色を入れる,メモを貼るなど).
繰り返しになりますが,本書はフローチャートの活用で漢方薬をうまく選択する第一歩となり得ることを明示した読本であり,漢方薬全般の理解および漢方薬の使い分けの根拠の一助となる良書です.
編集部より
漢方医学では,「証」や「気血水」などの症状・体質から治療法を決める.しかし,「用語が難しい」「どう活かせばいいかわからない」など困ることはないだろうか.
2023 年8 月に『症状・体質からしっかり選べる!薬剤師・登録販売者のための フローチャートでわかる漢方薬虎の巻』が発刊された.本書は,そんな漢方初心者にわかりやすいように,「漢方薬とは」「証とは」の基本から,漢方薬の特徴や使い分けを学べる書籍である.
Ⅲ章の「主訴・症状別 漢方薬の使い分け」はフローチャート形式の解説となっている.そのため,患者から症状を相談された際にまずは何を聞き取りどう判断していくかの流れが掴めるようになっている.また,漢方薬は「虚実」「寒熱」ごとにアイコンや色分けで区別されており,使い分けに必要な情報が自然と身につくよう工夫されている.
漢方薬の基礎から使い分けまでしっかりと学びたい方にこの1 冊で役に立つ,まさに「虎の巻」として活用いただければ幸いである.
2023 年8 月に『症状・体質からしっかり選べる!薬剤師・登録販売者のための フローチャートでわかる漢方薬虎の巻』が発刊された.本書は,そんな漢方初心者にわかりやすいように,「漢方薬とは」「証とは」の基本から,漢方薬の特徴や使い分けを学べる書籍である.
Ⅲ章の「主訴・症状別 漢方薬の使い分け」はフローチャート形式の解説となっている.そのため,患者から症状を相談された際にまずは何を聞き取りどう判断していくかの流れが掴めるようになっている.また,漢方薬は「虚実」「寒熱」ごとにアイコンや色分けで区別されており,使い分けに必要な情報が自然と身につくよう工夫されている.
漢方薬の基礎から使い分けまでしっかりと学びたい方にこの1 冊で役に立つ,まさに「虎の巻」として活用いただければ幸いである.