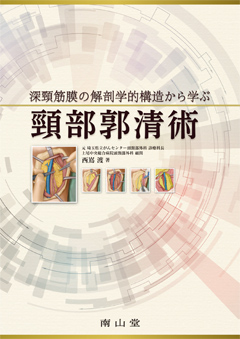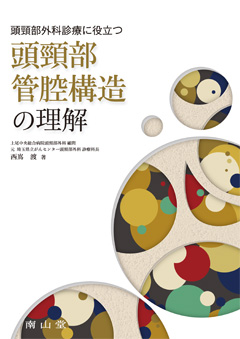頭頸部原発進行癌から嚥下機能を守る 喉頭温存術
1版
上尾中央総合病院頭頸部外科 顧問/
元埼玉県立がんセンター頭頸部外科 診療科長 西嶌 渡 著
定価
11,000円(本体 10,000円 +税10%)
- A4判 91頁
- 2025年8月 発行
- ISBN 978-4-525-31121-6
QOLを守る! 次世代外科医へ送る喉頭温存のための珠玉の知識
がん治療においてQOLが問われる時代.嚥下・発声・呼吸の機能を守る喉頭温存は,まさにその核心にある.40年にわたりがん治療最前線で患者と向き合ってきた筆者が臨床経験で得た知識と知恵を次世代へと伝える実践書.
- 序文
- 目次
序文
頭頸部原発進行がんの摘出術では,喉頭温存を意図する場合,嚥下機能の温存が重要である.嚥下機能は生まれながらに備わった機能であり,手術で口腔・咽頭の一部が切除されると必然的にこの機能は低下する.この低下した嚥下機能の状態で,喉頭を温存して誤嚥を未然に防ぎ,嚥下機能を確保することが頭頸部原発進行がんの手術の極みとなる.まさに執刀医の実力が試されるところである.
術後の誤嚥リスクを考慮し,喉頭を合併切除する医師もいるが,失声という障害を生じさせるため,その意義を執刀医は十分に自覚する必要がある.喉頭温存を最大限に考慮し,万策尽きた時に行うのが喉頭の合併切除であり,喉頭の摘出は第三級の傷害とされ,保険約款では死亡扱いである.また失声状態での仕事の継続は周囲の職場環境が受け入れてくれなければ難しいのが現状である.
喉頭が温存され嚥下できる利点は非常に大きい.経口摂取ができ会話ができることは,患者の尊厳を保ち,精神的なバランスを維持する上で重要である.喉頭の機能は,社会生活を営む上で必要不可欠なのである.
頭頸部進行がんの観血的治療は,ここ10年余りでその様相は一変した.進行例や初回加療後の非制御例に対する観血的治療の選択は著しく減少した.特に手術範囲に喉頭が含まれる場合,その傾向は顕著である.手術や放射線療法が主体だった時代には,初期治療が非制御に帰した症例に対して根治性を求めて手術が広く行われていたが,そのような時代が一掃されたといっても過言ではない.
その大きな分岐点は,分子標的治療の普及である.そして手術や放射線療法,化学療法併用症例の非制御例に対して分子標的治療が広く行われる現在では,根治手術は施行せず,分子標的治療が継続され,薬剤の種類を変えながら患者の受け入れ状態が許す限り継続される場合が多くなってきた.経済的な負担も決して小さくないが,その評価は後世に委ねられている.
化学療法や分子標的治療での制御が難しいのであれば,観血的治療に切り替えるのも一つの選択肢であるが,近年はそのような非制御例に対して手術によってがん摘出が可能であっても,術野に喉頭が含まれる場合には,手術を避ける環境が形成されつつあると言える.その結果として,分子標的治療を継続することになるが,根治に至らない場合も多く,投薬の中止とともに患者は主治医の手から離れ,以前よりも安易に“緩和医療に移行する”状況が発生している.
緩和医療に送られた段階で,頭頸部外科医の役割は終了するが,患者にとってはこれからが本当の戦いとなる.頭頸部原発がんが非制御状態で進行すると,嚥下障害が出現し,経管栄養や胃瘻の造設が必要となる.さらに誤嚥が激しくなり,呼吸困難や喀痰排出困難で気管切開が必要となるため,結果として失声と経口摂取ができない状態で終末期を迎えることになる.
喉頭の温存は,嚥下機能が安全に確保されることを大前提に行われ,まさに喉頭温存と嚥下機能とは表裏一体であり,嚥下機能から分離した喉頭の存在はあり得ない.したがって,術者は嚥下機能がいかなる生理的な機序でなされているのか,嚥下機能における喉頭の役割がどのようなものであるのかを理解した上で手術を行わなければならない.ゆえに本書の骨格は嚥下機能を温存することに視点を置いて,喉頭の温存術について筆者の経験を基に解説している.
筆者が本書を執筆しようとした第一の理由は,手術全盛時代を経験した医師が喉頭温存術に対してどのような考えで手術を施行していたのかを記録に残すためである.第二は,現状のように手術体験をする機会の少ない状況下では,執刀医が自らの体験を基に一から喉頭温存を試みる基準を作り上げるには未知の分野が広すぎて,喉頭温存の理論が構築できないのではないかと考えられるからである.手術は一から組み立てるのではなく,先人の知識を検証しながらそれを踏み台にして手術技術の改善に寄与する姿勢が,より深い経験となり,自身の手術技術,手術に対する考え方を確立すると同時に新しい治療方法の展開に繋がると思われるからである.
本書に記載された内容は,一医師が四十余年にわたり臨床現場に立ち続けることによって得られた経験と知見を述べたものである.頭頸部原発進行がんにおける喉頭の温存の概念の構築には,相当数の場数を踏まなければ確立できるものではなく,ある意味では医師個人に属する貴重な経験と言える.頭頸部がん治療の一線に立たれている方も,これから頭頸部がん治療を専攻しようとする方にも参考になる知見が含まれているものと思われ,その内容の是々非々を大いに批判していただきたい.そして本書の内容を踏み台にして,喉頭温存に対するご自身の治療概念を確立していただければ,筆者にとってこれに勝る喜びはない.
2025年6月
上尾中央総合病院頭頸部外科顧問
元 埼玉県立がんセンター頭頸部外科診療科長
西嶌 渡
術後の誤嚥リスクを考慮し,喉頭を合併切除する医師もいるが,失声という障害を生じさせるため,その意義を執刀医は十分に自覚する必要がある.喉頭温存を最大限に考慮し,万策尽きた時に行うのが喉頭の合併切除であり,喉頭の摘出は第三級の傷害とされ,保険約款では死亡扱いである.また失声状態での仕事の継続は周囲の職場環境が受け入れてくれなければ難しいのが現状である.
喉頭が温存され嚥下できる利点は非常に大きい.経口摂取ができ会話ができることは,患者の尊厳を保ち,精神的なバランスを維持する上で重要である.喉頭の機能は,社会生活を営む上で必要不可欠なのである.
頭頸部進行がんの観血的治療は,ここ10年余りでその様相は一変した.進行例や初回加療後の非制御例に対する観血的治療の選択は著しく減少した.特に手術範囲に喉頭が含まれる場合,その傾向は顕著である.手術や放射線療法が主体だった時代には,初期治療が非制御に帰した症例に対して根治性を求めて手術が広く行われていたが,そのような時代が一掃されたといっても過言ではない.
その大きな分岐点は,分子標的治療の普及である.そして手術や放射線療法,化学療法併用症例の非制御例に対して分子標的治療が広く行われる現在では,根治手術は施行せず,分子標的治療が継続され,薬剤の種類を変えながら患者の受け入れ状態が許す限り継続される場合が多くなってきた.経済的な負担も決して小さくないが,その評価は後世に委ねられている.
化学療法や分子標的治療での制御が難しいのであれば,観血的治療に切り替えるのも一つの選択肢であるが,近年はそのような非制御例に対して手術によってがん摘出が可能であっても,術野に喉頭が含まれる場合には,手術を避ける環境が形成されつつあると言える.その結果として,分子標的治療を継続することになるが,根治に至らない場合も多く,投薬の中止とともに患者は主治医の手から離れ,以前よりも安易に“緩和医療に移行する”状況が発生している.
緩和医療に送られた段階で,頭頸部外科医の役割は終了するが,患者にとってはこれからが本当の戦いとなる.頭頸部原発がんが非制御状態で進行すると,嚥下障害が出現し,経管栄養や胃瘻の造設が必要となる.さらに誤嚥が激しくなり,呼吸困難や喀痰排出困難で気管切開が必要となるため,結果として失声と経口摂取ができない状態で終末期を迎えることになる.
喉頭の温存は,嚥下機能が安全に確保されることを大前提に行われ,まさに喉頭温存と嚥下機能とは表裏一体であり,嚥下機能から分離した喉頭の存在はあり得ない.したがって,術者は嚥下機能がいかなる生理的な機序でなされているのか,嚥下機能における喉頭の役割がどのようなものであるのかを理解した上で手術を行わなければならない.ゆえに本書の骨格は嚥下機能を温存することに視点を置いて,喉頭の温存術について筆者の経験を基に解説している.
筆者が本書を執筆しようとした第一の理由は,手術全盛時代を経験した医師が喉頭温存術に対してどのような考えで手術を施行していたのかを記録に残すためである.第二は,現状のように手術体験をする機会の少ない状況下では,執刀医が自らの体験を基に一から喉頭温存を試みる基準を作り上げるには未知の分野が広すぎて,喉頭温存の理論が構築できないのではないかと考えられるからである.手術は一から組み立てるのではなく,先人の知識を検証しながらそれを踏み台にして手術技術の改善に寄与する姿勢が,より深い経験となり,自身の手術技術,手術に対する考え方を確立すると同時に新しい治療方法の展開に繋がると思われるからである.
本書に記載された内容は,一医師が四十余年にわたり臨床現場に立ち続けることによって得られた経験と知見を述べたものである.頭頸部原発進行がんにおける喉頭の温存の概念の構築には,相当数の場数を踏まなければ確立できるものではなく,ある意味では医師個人に属する貴重な経験と言える.頭頸部がん治療の一線に立たれている方も,これから頭頸部がん治療を専攻しようとする方にも参考になる知見が含まれているものと思われ,その内容の是々非々を大いに批判していただきたい.そして本書の内容を踏み台にして,喉頭温存に対するご自身の治療概念を確立していただければ,筆者にとってこれに勝る喜びはない.
2025年6月
上尾中央総合病院頭頸部外科顧問
元 埼玉県立がんセンター頭頸部外科診療科長
西嶌 渡
目次
第1章 頭頸部進行がんに対する拡大摘出手術の歴史的推移
1 DP皮弁の出現
2 手術技術の経験と伝承の重要性
3 分子標的治療の制御例に対する対応
第2章 嚥下機能の第2相に関与する咽頭管腔構造の理解
1 食塊の経路の領域的分類
2 拡大咽頭腔の部分切除が喉頭の上下運動(嚥下機能)に及ぼす影響
3 喉頭温存の理論的裏付け
4 生体における喉頭の挙上運動のメカニズム
5 生体における喉頭の存在様式
6 手術操作における頸椎前面部分の処理方法
7 ヒトにおける中咽頭の特異性
8 喉頭の可動性が嚥下機能に与える影響(下咽頭進行がん症例における検討)
9 喉頭が上下運動するための喉頭周囲の解剖学的構造
10 臨床現場における上喉頭神経麻痺の特徴
11 喉頭本体の生理機能の複雑性
12 嚥下機能に直結する神経群
13 軟口蓋を形成する筋肉と神経
14 拡大咽頭管腔構造の外側から喉頭を挙上させる筋肉
第3章 嚥下機能の第1相に関与する舌・口腔の生理学・解剖学の理解
1 病巣の切除部位直下に存在する筋肉や神経・脈管を可能な限り温存する
2 脳内の器質的障害による半身麻痺と,嚥下神経機能の脱落による嚥下障害の違い
3 患者の違いが手術の効果の違いに及ぼす影響
4 非制御例に対して,嚥下機能が確保できた喉頭温存のための根治的手術療法
5 咽頭への感覚のある口腔・咽頭粘膜の残存
第4章 舌進行がんに対する喉頭温存の工夫
1 舌進行がんが潜在性舌内リンパ節に及ぼす影響
2 舌進行がんにおける舌の切除範囲と喉頭温存の工夫
第5章 中咽頭進行がんにおける喉頭温存の工夫
1 頸椎前面の処理
2 中咽頭進行がんの切除範囲と喉頭温存の具体例
第6章 喉頭がん・下咽頭がんにおける喉頭温存の工夫
1 喉頭の後方に存在する拡大咽頭管腔構造と咽頭収縮筋群との位置関係
2 喉頭がんにおける部分切除
3 下咽頭がんにおける部分切除
4 喉頭がん・下咽頭がんにおける喉頭温存術施行時の手術手技的な注意事項
第7章 頸部郭清術が嚥下機能に影響を及ぼす背景
1 舌咽・迷走・舌下の3種類の脳神経と内頸動脈および外頸動脈との位置関係
2 内頸動脈の裏面の操作
3 頸部郭清術そのものが咽頭の粘膜に及ぼす影響
4 喉頭の発声機能に関わる筋肉と神経
5 喉頭内を走行する反回神経と喉頭内筋肉群の位置関係
6 喉頭に入る動脈と神経の走行
7 音声障害
8 口唇の密閉
日本語索引
外国語索引
1 DP皮弁の出現
2 手術技術の経験と伝承の重要性
3 分子標的治療の制御例に対する対応
第2章 嚥下機能の第2相に関与する咽頭管腔構造の理解
1 食塊の経路の領域的分類
2 拡大咽頭腔の部分切除が喉頭の上下運動(嚥下機能)に及ぼす影響
3 喉頭温存の理論的裏付け
4 生体における喉頭の挙上運動のメカニズム
5 生体における喉頭の存在様式
6 手術操作における頸椎前面部分の処理方法
7 ヒトにおける中咽頭の特異性
8 喉頭の可動性が嚥下機能に与える影響(下咽頭進行がん症例における検討)
9 喉頭が上下運動するための喉頭周囲の解剖学的構造
10 臨床現場における上喉頭神経麻痺の特徴
11 喉頭本体の生理機能の複雑性
12 嚥下機能に直結する神経群
13 軟口蓋を形成する筋肉と神経
14 拡大咽頭管腔構造の外側から喉頭を挙上させる筋肉
第3章 嚥下機能の第1相に関与する舌・口腔の生理学・解剖学の理解
1 病巣の切除部位直下に存在する筋肉や神経・脈管を可能な限り温存する
2 脳内の器質的障害による半身麻痺と,嚥下神経機能の脱落による嚥下障害の違い
3 患者の違いが手術の効果の違いに及ぼす影響
4 非制御例に対して,嚥下機能が確保できた喉頭温存のための根治的手術療法
5 咽頭への感覚のある口腔・咽頭粘膜の残存
第4章 舌進行がんに対する喉頭温存の工夫
1 舌進行がんが潜在性舌内リンパ節に及ぼす影響
2 舌進行がんにおける舌の切除範囲と喉頭温存の工夫
第5章 中咽頭進行がんにおける喉頭温存の工夫
1 頸椎前面の処理
2 中咽頭進行がんの切除範囲と喉頭温存の具体例
第6章 喉頭がん・下咽頭がんにおける喉頭温存の工夫
1 喉頭の後方に存在する拡大咽頭管腔構造と咽頭収縮筋群との位置関係
2 喉頭がんにおける部分切除
3 下咽頭がんにおける部分切除
4 喉頭がん・下咽頭がんにおける喉頭温存術施行時の手術手技的な注意事項
第7章 頸部郭清術が嚥下機能に影響を及ぼす背景
1 舌咽・迷走・舌下の3種類の脳神経と内頸動脈および外頸動脈との位置関係
2 内頸動脈の裏面の操作
3 頸部郭清術そのものが咽頭の粘膜に及ぼす影響
4 喉頭の発声機能に関わる筋肉と神経
5 喉頭内を走行する反回神経と喉頭内筋肉群の位置関係
6 喉頭に入る動脈と神経の走行
7 音声障害
8 口唇の密閉
日本語索引
外国語索引